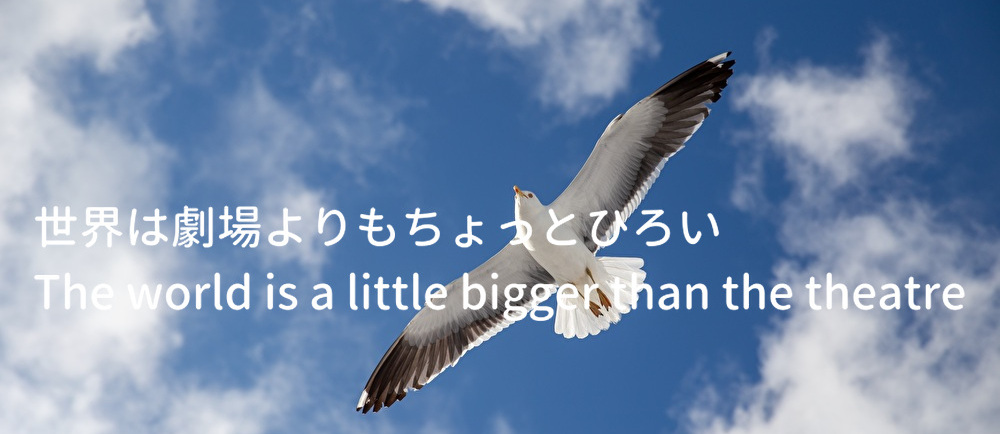
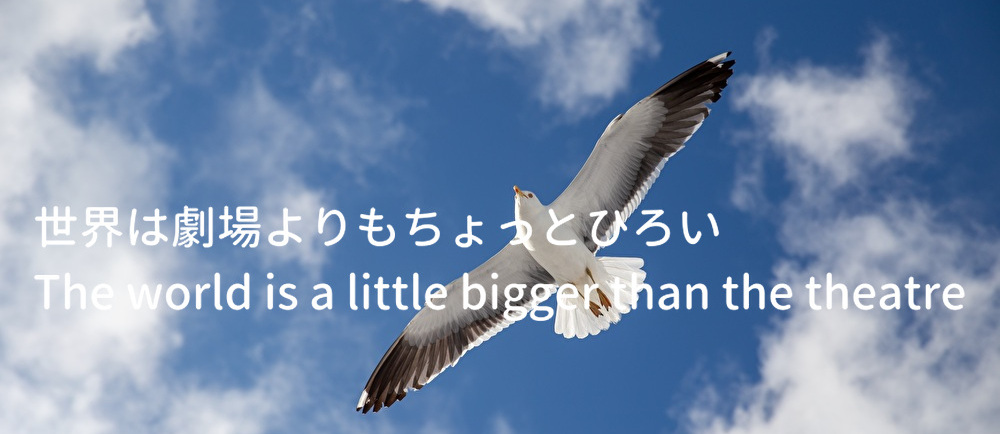
7月31日
『ピン・ポン』、11時と17時の二回上演。
どちらの上演にも、30人以上の幼稚園児が客席最前列に並ぶ。
エネルギーあふれる彼らのリードで、今日も生き生きとした「劇場」が生まれる。
終演後、ウィーンの劇場から上演の打診。
打ち上げは、劇場近くの焼肉屋で。
7月30日
『ピン・ポン』、初日。
客席の子どもたち、そして大人たちの和やかな反応に舞台が弾む。
七年前に出会って、通い続けてきた(去年だけお休み)キジムナーフェスタ。
子どもたちとの芝居についてはすべてここで学んだ。
たくさんのこころみを許してくれたプロデューサーの下山さんに、あらためて感謝。
7月29日
コザ、あしびなー劇場のある市立の複合施設二階に仮設された、町中劇場スペース1で、『ピン・ポン』の準備作業。
隣のスペース2で幕を開けているインドの人形劇団と時間をシェアしながらの進行。
照明・横原、音響・勝見、舞台監督・廣瀬、出演の久保、光田、そしてフェスティバル側の助っ人スタッフ、終日、奮闘す。
作業を終えて、夜九時前、一回目の舞台稽古。
座・高円寺とは、間口で二分の一ほどの小スペースでの、『ピン・ポン』キジムナーフェスタ版が、どうやら無事に完成した。
7月28日
今日から沖縄。
迎えてくれた青空と白い雲と、いまこの場所に負わされている、あるいは負わせっぱなししてしまっている現実とのギャップ。
空港から出迎えのバスで高速道路コザへ向かう途中、黒テントで初来沖以来のさまざまな思いが走馬灯のように巡る。
しかし、とにもかくにも、まずは、キジムナーフェスタ。
与えられた場を未来への架け橋とする自分たちなりの役割をきちんと果たそう。
7月27日
ライボー(ロンドン銀行間取引金利)の不正操作。
野村證券のインサイダー取引。
間違いなく氷山の一角だろうが、同時に、氷山本体の想像を絶する巨大さに背筋が凍る。
経済についての知識も定見もない素人目にも、金融(投機)資本主義の末期的光景は明らか。
「格差」などと生易しい言葉ではとうてい括りきれない、圧倒的大多数が徘徊させるべき「妖怪」の名は?
7月26日
子どもと舞台芸術出会いのフォーラム2012、シンポジウム「アンダー3(三歳以下)のための舞台芸術-その可能性を探る」のコーディネーターをつとめる。
小森美巳(演出家)、西田豊子(劇作家、演出家)、永野むつみ(人形遣い)という、個性あふれる三人の女性パネリストからは、刺激的な話題が次々に。
100人を越える熱心な参加者に、主題の可能性と切り口のとば口くらいは伝えられただろうか。
終わって、啓子と表参道で待ち合わせて、刺繍作家吉元れい花さんの展覧会へ。
繊細にして官能的な、いかにもれい花さんらしい華麗な世界。
7月25日
『ふたごの星』、プレ稽古とスタッフ会議。
映像の飯名尚人さんなどあたらしいメンバーも何人か加わって、新鮮な打ち合わせ。
再演を重ねながら劇場レパートリーを育てていくという座・高円寺のやり方が、いつか「フツー」になるのを楽しみに。
今日はそのほか、『霊戯』(2012年版)構成台本にも着手。
作者郭宝崑との対話は、いつもの通り、ぴしっと背筋をのばして。
7月24日
夜に眠り、朝に目覚める。
繰り返される自然の波動にたいして、自分のからだとこころがうまく同期しないのは何故だろう。
目覚めてもどこか眠っている。
眠ってもまだ覚めている。
古人曰く、夢は五臓の疲れ、とか。
7月23日
なにかが始まっている。
いや、終わろうとしている。
おそらく誰もが気づいている。
なのに、不思議なほどの沈黙。
いまをではなく、明日について語るとき。
7月22日
『ピン・ポン』三日間の上演を終えて千穐楽。
このあと月末にキジムナーフェスタ(沖縄市)、秋には旅上演も待っている。
世田谷パブリックシアターの「子どもの劇場」から数えれば、かれこれ二十年近く。
ようやく、自分なりに納得できる子どもたちへの舞台づくりがかたちになった。
何気なく、軽やかに┄┄そして楽しく(見える!)。
7月21日
土曜日の座・高円寺。
エントランスでは月に一度の「座の市」。
あいにくの雨模様だったが、赤いテントの下、焼きたての酵母パン、江戸野菜そのほか、小さな賑わい。
劇場に入ると絵本を中心にした古本市と、『ピン・ポン』の開演を待つ親子連れ。
小さな子どもたちの元気のいい声が響く、思い描いていた劇場のひとつの姿。
7月20日
『ピン・ポン』初日。
客席で子どもたちの反応を感じながら、去年上演した時の手応えを思い出す。
素直に目の前の「真実」に向き合うひとりひとりの息づかいがパフォーマーに伝わり、緊張感とここちよさが同時に存在する劇場の時間が紡ぎだされていく。
終演後の暖かな拍手。
見に来てくれたたくさんの友人たちの笑顔がうれしい。
7月19日
『ピン・ポン』、舞台稽古。
舞台と観客席との双方向のやりとりを頼りとする演出作業ににとって、子どもたちの多い観客席には覚悟がいる。
ふだんの方法論である「突き放す」という信頼感の示し方ではなく、「突き放される」ても大丈夫というおおらかさとでも言えばいいか。
音楽担当の磯田さん曰く、「世の中を面白くするための日々の精進」。
だよね。
7月18日
一昨日あたり、東京も梅雨明けしたらしい。
庭の紫陽花は元気にたくさん花をつけたが、今年は梅雨を感じる日が極端に少なかったような。
雨が「しとしと」降りつづく梅雨の季節がそんなに嫌いではないせいもあって、何だかちょっと損をした気分。
このところ、毎年、同じ頃に同じような感想を記しているが、最近の東京は間違いなく亜熱帯の気候。
それとも、季節を感じるこちらの皮膚感覚の衰えだろうか。
7月17日
『ピン・ポン』、劇場仕込み日。
再演ということもあり、作業をtupera tuperaの亀山、中川さん(美術)とスタッフにまかせて、事務所でひとり、月末に稽古がはじまる『ふたごの星』の台本整理。
流れをDVDで確認しながら、演出の新構想についていろいろ。
夜、演出の流山児祥、来館。
来年度の新企画についての話を聞く。
7月16日
言葉が必要だ。
言葉のためには考えなければ(遊ばなければ)。
考えるためには本を読まなければ(面白い本と出会わなければ)。
本を読むためには時間をつくらなければ(ただ机に向かっていても本は読めない)。
限られた時間の使い方を工夫しなければ(使い物になる時間は、おそらくほんのわずか)。
7月15日
秋から冬にかけての上演活動、年明けからの座・高円寺企画など、体制準備の締切り間近。
とりあえず、上演台本執筆や再構成が四作品。
これから二カ月あまりの予定表に、作業の見通しを割りつけていく。
うーむ、今年の夏休みは宿題が多そう。
日程表づくりでひと安心という、小学生以来の悪癖に用心。
7月14日
稽古、休み日。
雨降りの予想だったが、日差しのある真夏日(このところ、予報官泣かせに違いない不安定な天気がつづく)。
昼過ぎ、母、新盆のため、菩提寺のご住職が棚経に来訪。
自宅で聞く経文は、いつもとは違う趣でこころを落ち着かせる。
今日は檀家七軒をまわる予定が、連休初日の交通渋滞でどうやら一軒あきらめなくてはと、ご住職、微苦笑。
7月13日
『ピン・ポン』稽古、最終場面まで。
50分足らずの作品だが、シーンふたつを大幅に作り替えて、ようやく全体の流れがすっきりとした。
美術のほかに演出も手伝ってくれている、絵本作家ユニット、tupera tuperaの亀山さん、中川さんの的確な指摘、音楽磯田さんのひょうひょうと見えて繊細なサポートがうれしい。
あたらしく近郊のホールからの上演申し込みなど、自主製作作品の再演、レパートリー化も、少しずつ軌道に乗り始めている。
稽古を終わって、今週も永田町方面へ。
7月12日
劇場創造アカデミー第Ⅰ期修了生の弓井茉那、下村界と、『あらしのよるに』稽古。
ふたりは昨年オーディションで選ばれて、イタリアの演出家とともにこの作品を、沖縄のキジムナーフェスタで上演した。
舞台は好評で、今年も再演。
狼の若者と羊の少女が嵐の夜に暗闇で出会い、禁断の恋におちる。
有名な童話作品を下敷きに、イタリア好みのスパイシーな味付けが見事。
7月11日
私たちが共有しなければならない喫緊の課題とは何か。
まず、「私たち」のひろがりと境界とをはっきりと位置づけること。
主体は「私」ではなく、あくまでも「私たち」なのだから。
「私たち」にとっての大文字の敵対物をはっきりと見定めること。
現在の「サイカドー、ハンタイ!」から、より本質的な、「私たち」自身のsingle issueを掴み取り、引きずり出してみせること。
7月10日
母の初盆。
菩提寺に墓参り。
昨日につづく真夏日だったが、青空と白雲のコントラストが爽快。
墓のある港区は、中学三年から二十二歳の最初の結婚まで、両親と弟たちと一緒に過ごした町。
墓の背景にそびえている東京タワーが、間に建ったビルに遮られて頂上部分しか見えなくなってしまったのがちょっと惜しい。
7月9日
まるで真夏の日差し。
二カ月に一度の定期検診を終えて、高円寺。
お盆を前に(んな訳ない)床屋で頭を丸め、『ピン・ポン』稽古へ。
舞台の上から余計なものを取り除いていく度に、反対に、少しずつ舞台の上の世界がひろがっていく。
不思議だが、ほんとうだ。
7月8日
今村信雄『落語の世界』(平凡社ライブラリー)。
父子二代にわたる落語速記者二代目の三代目小こさんからの聞き書きを中心にした寄席芸人録。
明治、大正からぼくにも思い出のある昭和の噺家まで、登場人物ひとりひとりへの愛情あふれる人物描写がうれしい。
先代正蔵が懐古していた一朝老人が、「分身くらべ」の章に微笑ましい役回りで登場。
菜の花屋双蝶とか、電鉄庵馬楽とか、寄席という小劇場に蠢いていた人びとへの思いはつきない。
7月7日
七夕、座・高円寺の小フェスチバル「世界を見よう!」、はじまる。
『ピン・ポン』稽古後、最初の演目、シアター・リフレクション(デンマーク)の『星のおくりもの』を小さな観客たちと一緒に観劇。
舞台裏に張られた白い特製テントの中、40人ほどの観客を前に演じられる、いかにもリフレクションらしい、微笑ましい仕掛け満載のファンタジー。
一階ロビーでは、恒例の古本・雑貨市、「本の楽市」を同時開催。
こちらでは、劇画作家つげ忠男の初版本二冊(格安)を見つけ、早速、購入。
7月6日
稽古後、高円寺から四谷経由で、地下鉄、国会議事堂前へ。
電車を降りると、駅構内から、警官、多数。
一カ所だけ開けてある地上階段へ、手際よく誘導(以後、ほとんどすべて、事前に用意された彼らのシナリオに従って進行)。
声がけの言葉が、先週の「集会ですか?」から、「抗議の方はこちら」に変わっていた。
小雨降るなか二時間、今日も人びととともに、「その場所」(ようするに、ここも劇場か?)に、ただ佇む。
7月5日
さあ、明日から『ピン・ポン』の稽古。
去年の上演ビデオを確かめながら、進行台本を書き直した。
見た目にはそれほど大きな変化はなくても、細部のやりとりへの工夫とか、場面ごとのテンポ感の整理とか、劇場レパートリーとしてさらに成長させるための手直しいろいろ。
あっと言う間の半年間、今年はこれまで、けいこ場は先日のリーディング『走れメロス』だけ。
技術監督の鈴木章友くんが下準備するけいこ場の様子をのぞいて、さすがに頬がゆるむ。
7月4日
座・高円寺事務所に、和田ちはるさん来訪。
和田さんは、ドイツの作曲家ハンス・アイスラーの研究者。
三十年ほど前に黒テントで上演した、ブレヒト+アイスラー『処置』(上演時の題名は『「処置」、および「処置」について』)をめぐる聞き取り調査。
廃坑から出現した亡霊たちが演じる『処置』というコンセプトで、亡くなった村松克巳はじめ四人の俳優たちが、コンクリートで塗り固めた外套をまとい、濛々と埃を舞あげながら登場した。
上演当時の協働者、作曲家の林光さん、訳詩をお願いした高橋悠治さん、合唱指揮を手伝っていただいた田中信昭さん、ピアノ演奏の志村泉さん┄┄充実した顔ぶれだった。
7月3日
会議や打ち合わせで使う「説明の言葉」が、いつの間にか「説明のための言葉」になってしまう。
用心しなければならない。
上手な、あるいは説得的な説明は、内容の正確さを意味しない。
立て板に水の論理性とか、的確な比喩は、しばしば単なる同義反復に過ぎない。
言葉を操るのではなく、言葉を発しなければ。
7月2日
書斎前にプランターで育てている朝顔が、毎朝、四、五輪花をつける。
去年のゴーヤはうまくいかなかったが、今年は肥料が効いたらしい。
気休め半分の日除けのつもりが、素直で儚げな花の彩りが、思いがけない楽しみになった。
大飯原発、再稼働。
「朝顔に 釣瓶とられて もらい水」┄┄という日々の暮らしの感性を、私たちはどこで失ってしまったのだろうか。
7月1日
雨、しめやかに。
今年は梅雨はどこかにいってしまったのか。
それとも「宣言」はこれからなのか。
季節のうつろいに触れながら、日々、再生を繰り返す。
こころもからだも┄┄だったはずなのだが。
